小学校の女子トイレに潜む怪異
「赤い紙が欲しい?青い紙が欲しい?」
その声が聞こえた瞬間、逃げなければならない──。
日本全国の学校、特に古びた木造校舎を持つ地方の小学校では、昔から“赤マント”の噂が囁かれてきた。
決まってその舞台は、校舎の端にある女子トイレの一番奥の個室。掃除されずカビ臭いその空間で、一人で用を足していると、突然背後から囁くような声が聞こえてくるという。
「赤い紙が欲しい?……それとも、青い紙?」
選択肢は二つ──だが、どちらを選んでも死が待っている。
赤を選ぶと身体中を切り裂かれ、血まみれにされる。
青を選ぶと窒息死──顔が真っ青になるまで首を絞められる。
無言を貫いても、個室のドアが勝手に開き、赤いマントを着た存在が立っているという報告も存在する。
誰も助けには来ない。すでにトイレに足を踏み入れたその瞬間から、“選択”は始まっていたのだ。
この怪談には、“自分が選択を迫られる”という心理的圧迫がある。逃げ場がない密室、声の主が見えない状況、そして選んでも選ばなくても死が訪れるという構造は、日本人が持つ“集団圧力”や“沈黙の恐怖”と密接に関わっているのかもしれない。
戦後から広がる“マント男”の原型
昭和初期、戦後間もない日本にて、「赤いマントと仮面をつけた男が子どもに声をかける」という新聞記事がいくつか掲載されている。
その多くは学校やその周辺、公衆トイレなどに現れる不審者の報告だった。
- 白手袋をつけていた
- 顔に包帯を巻いていた
- 赤いマントを羽織っていた
これらの特徴が混ざり合い、現在の“赤マント”という怪異像が形成されていった。
やがてそれは“人間の変質者”という枠を超え、霊的存在や都市伝説の域に達するようになる。
1970〜80年代の学校の怪談ブームを経て、児童書・マンガ・TVの影響で“現代妖怪”化し、赤マントは完全に定着した。
また、昭和50年代にはPTAや学校側が真剣に“赤マントの出現”に対応しようとした記録も残っており、一部の学校では実際にトイレの使用時間を制限する通達まで出されたという。
子どもたちの恐怖が、現実の教育現場を揺るがしたのだ。
この現象の背景には、日本社会における“清潔”と“排泄”に対するタブー視が深く関わっている可能性がある。トイレという“誰にも見られたくない場所”で起きる怪異という構造は、人の深層心理に直接刺さる。
その選択に意味はあるのか?
都市伝説として語られる赤マントの本質的な怖さは、“どちらを選んでも助からない”という回避不能な選択の構造にある。
これは心理的な“詰み”であり、プレイヤーが絶対に勝てないゲームだ。
日本の他の怪異(くねくね、カシマレイコ、ドッペルゲンガーなど)にも共通するのは、
- 無視しても襲われる
- 正解のない選択肢
- 見てしまったら終わり
この“どう足掻いても救われない構造”が、赤マントという存在に特有の絶望感を与えている。
さらに興味深いのは、地域によってこの“選択肢”にバリエーションが存在することだ。
- 「トイレットペーパーが欲しいですか?」という質問形式
- 「赤の紙、青の紙、それとも白の紙?」という三択パターン
- 「赤を選ぶとあなたは死ぬ。青を選ぶと家族が死ぬ」という心理系選択
また、“沈黙”が最も悪手とされる地域もあり、必ず何かを答えなければならないというルールが存在する場所もある。
このように、赤マントは時代と共に変異し続ける恐怖装置なのだ。
赤マントの派生怪異たち
赤マントの人気と恐怖構造は、後の“選択系怪異”の礎となった。
たとえば「青マント」「紫マント」などの派生バリエーションも存在する。
- 青マント:赤マントと同様にトイレで現れ、青を選んだ者は“水に引きずり込まれて溺死”すると言われる。
- 紫マント:声だけでなく、実体を伴って出現するタイプのバリエーションで、顔を隠している場合が多く、その顔を見ると即死するとも。
さらに、色の違いによって“死に方”が分岐するタイプの都市伝説も存在する。
これらは子供同士の“話の遊び”として発展したとも考えられるが、
地域によっては「実際に見たことがある」という目撃談も報告されている。
また、マンガやホラーゲームで赤マントが登場したことで、現代でもそのイメージは強烈に根付いている。
実話との境界──似た事件の存在
都市伝説として語られる“赤マント”には、実在した事件との類似点も存在する。
1990年代、東京郊外の公園で子供に声をかけていた“赤いコートの男”が補導された事件があり、
また、2000年代にはとある学校で「トイレで“赤いマント”を見た」という報告が複数上がり、地元警察が調査に入った例も存在している。
もちろん、都市伝説の影響を受けた悪戯や模倣犯である可能性は高いが、
“現実と虚構の境目”が曖昧になってしまうのも、こうした怪談の恐ろしさなのだ。
さらに、一部の都市伝説系サイトやオカルト掲示板には、
「実際に赤いマントの男に追いかけられた」
「トイレの天井裏から見られていた気がする」
といった、怪談と現実が交錯した体験談が投稿されており、完全なフィクションと断定するのは難しい部分も残っている。
投稿主のコメント
子供のころ、確かに“トイレの一番奥には入っちゃダメ”という暗黙のルールがあった。
特に放課後、誰もいない校舎でトイレに行くと、空気の重さが違った気がする。
赤マントの話を知ったのは小学校3年生のとき。怖いもの見たさで友達と肝試しに行ったが、誰も最奥の個室には入れなかった。
もしあのとき声が聞こえていたら、僕らは無事でいられただろうか?
大人になった今でも、公共施設のトイレで“誰もいないのにドアが閉まる音”が聞こえると心臓が跳ね上がる。
あの選択肢は──いつでも僕らの背後に潜んでいるのかもしれない。





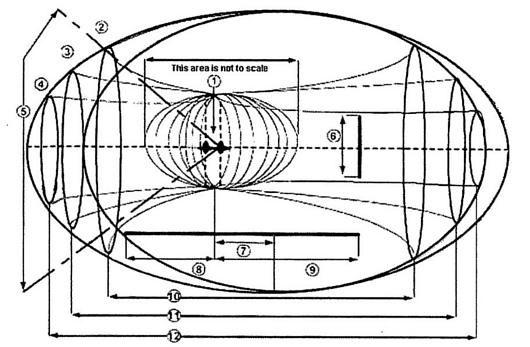













コメント