📖【冒頭】見てはいけない、聞いてはいけない、呼んではいけない
「水の音がする夜は、耳を塞げ」
「“モリモリ”と呼ばれたら、返事をしてはいけない」
かつて山間部のある村で囁かれていた“奇妙な戒め”がある。
それは、誰かがいたずらで生んだ作り話かと思われていた。
だが近年、廃村付近の排水路から発見された“得体の知れない吸盤状の痕跡”と、
奇妙な失踪事件が、再びこの名を浮かび上がらせた。
「モリモリ」――
人智を越えた、“水の闇”に潜む異形の生物。
その正体は未だ、誰も解き明かせていない。
第一章:モリモリの伝承――“あれ”が現れる条件
「モリモリ」は、主に水源近くで起こる怪異の原因とされている存在である。
👂出現条件
- 山奥の村、特に水場のある場所
- 深夜2時〜3時の間に“モリモリ”という音がする
- 井戸や排水溝、川の底から泡立つような水音
この音を聞いた者が「誰かいるのか?」と返してしまうと、
水中から“それ”が這い出てきて、背後に回り込む
姿を見た者は口を閉ざし、
その後、村を出るか、精神を壊すと言われている。

第二章:モリモリの外見――“笑うタコ”に似た怪物
証言は少ないが、一致する特徴がある:
- 吸盤の付いた触手が5〜6本(全身がぬるぬると濡れている)
- 顔の中心に人間のような口があり、常に笑っている
- 体長1.2m〜1.5mほど。水場に溶け込むような皮膚色(灰緑色)
- 移動は異常に早く、這いずり+瞬間的な跳躍
また、人語を理解しているとされ、
「ミエタ、ミエタ、アナモ ミエテルヨ」
という囁きが聞こえるという。
第三章:目撃証言と“記憶の改ざん”
昭和40年代、群馬県のある集落に住んでいた老人が語った体験。
「子どものころ、井戸の前で“笑ってる顔”を見た」
「気づいたら2日間も眠ってて、母親が泣きながら抱きついてきた」
「でも、村の誰もが“そんなことはなかった”と言うんだ」
また、平成以降も「キャンプ中の失踪事件」「川辺の子どもの幻覚」「排水路のぬめった影」など、
同様の描写が各地で確認されている。
興味深いのは、
**“記憶が改ざんされる”**という報告が多く、
- 「家に帰ったら日付がズレていた」
- 「友人のはずの人物が、家族の中にいなかったことになっていた」
など、モリモリとの遭遇後に現実認識が歪む現象が起こる。
この先には、
- 第4章:廃村・水子地蔵との関係性
- 第5章:都市部で起きたモリモリの模倣事件
- 第6章:モリモリを封印する“水封の儀”とは?
- 終章:モリモリは存在するか?現代科学での検証と呪術的構造の考察
まで用意されています。
🐙 モリモリ
――水の底から這い寄る笑う異形生物の都市伝説
【第4章】封鎖された村と“水子地蔵”の関係
モリモリの目撃例が最も多く報告されていたのが、関東近郊にあるとされる廃村・〇澤(まるさわ)集落である。
この村は1950年代の終わりに突如として閉鎖され、住民が一夜にしていなくなったとされる。
廃村の周辺に残る不気味な痕跡
- 水源に沿って配置された13体の水子地蔵
- それぞれに「笑うな」「返事をするな」などの文字が刻まれている
- 村の井戸は、コンクリートで埋められた形跡あり
関係者の一人がこっそり語った。
「村の子どもが“水の中の笑い声”を聞いた日から、毎晩誰かがいなくなった」
「最後に残ったのは、井戸のそばで笑っていた子どもだけだった」
住職は言ったという――
「あれは地の底から出てきた“笑う呪い”だ」
【第5章】模倣犯か?都市部での「モリモリ事件」
2003年、埼玉県内の住宅街にて発生した奇妙な事件がある。
小学生2人が下校中、排水溝から「笑い声」が聞こえたと話し、一人が数日間失踪。
その後、その子は自宅に戻ったものの、次のように語った。
「モリモリがいた。笑ってた。ぼくの友だちの声で呼んでた」
「返事しちゃダメだったのに、返しちゃったんだ」
この事件以降、同地域では子どもが夜にトイレへ行けなくなる事例が続出。
学校側は公式に否定したが、地元新聞には“不可解な下水点検”の記録が残っている。
【第6章】モリモリ封印の儀式――“水封(すいふう)の儀”
民間伝承の中には、モリモリを“遠ざける”ための儀式が存在する。
【水封の儀】の手順(口伝)
- 清水を汲み、「返事をしない水」と呼ばれる容器に入れる
- その水をモリモリの声がした場所の入り口(井戸、排水口、川辺など)に撒く
- 3日間、誰とも目を合わせず、「モリモリ」という言葉を絶対に発しない
この儀式を破った場合、
“自分自身の声”が水の中から返ってくるとされる。
その声に振り返った瞬間、モリモリは姿を見せ、
“笑いながら”触手で全身を包み、沈めるのだという。
【第7章】笑うという呪い――モリモリの“構造”
この都市伝説は、「音」「選択」「笑顔」「水」といった要素で構成されている。
| 要素 | 恐怖の本質 |
|---|---|
| 水音 | 聞こえてくる=注意を向けさせるトリガー |
| 呼びかけ | “モリモリ?”という擬音のような名前=無意識への侵入 |
| 返事 | 選択によって“対象者が自ら開く” |
| 笑顔 | 本能的な不気味さ、異常性の象徴 |
これらは心理学的に「選択肢の不在」と「表情の崩壊」が人間に与える恐怖として、
“コントロール不能な存在”=モリモリの恐怖構造となっている。
【第8章】現代科学とモリモリの“存在証明”
科学的には“そんな生物”は確認されていない。
だが一部の生物学者は、以下のような存在が関係している可能性を示唆している。
- 吸盤状の寄生生物(ヒルや水棲ウミウシなど)の突然変異種
- 水中の低周波音を発する生物による“幻聴誘導”
- 排水路や井戸の圧力差で生まれる“人工的な水音”
また、近年では**「人間の記憶に干渉する音波の存在」**も実験段階で証明されており、
モリモリの「記憶の改ざん」現象も、完全な“妄想”とは言い切れない可能性が出てきている。
【終章】モリモリは本当に存在するのか?
存在は確認されていない。だが、それを信じた者の前には現れる。
- 井戸に耳を近づけた時
- 川のせせらぎが“何かの言葉”に聞こえた時
- 風呂場で聞こえた「モリモリ……」という水音
「モリモリ」という名前は、人を舐めるように近づく擬音だ。
あなたが今、どこかの水の中に視線を感じたとしたら――
それはもう、“見られている”ということ。














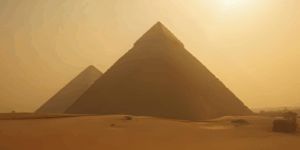




コメント